うめAUDIO(仮称)
作例集・回路図・素人解説 周辺回路1
|
・汎用電源回路1・2 ・汎用電源回路3(可変) ・汎用電源回路4(可変改) ・電源連動ミュート回路 ・電源連動ミュート回路(可変電源対応) |
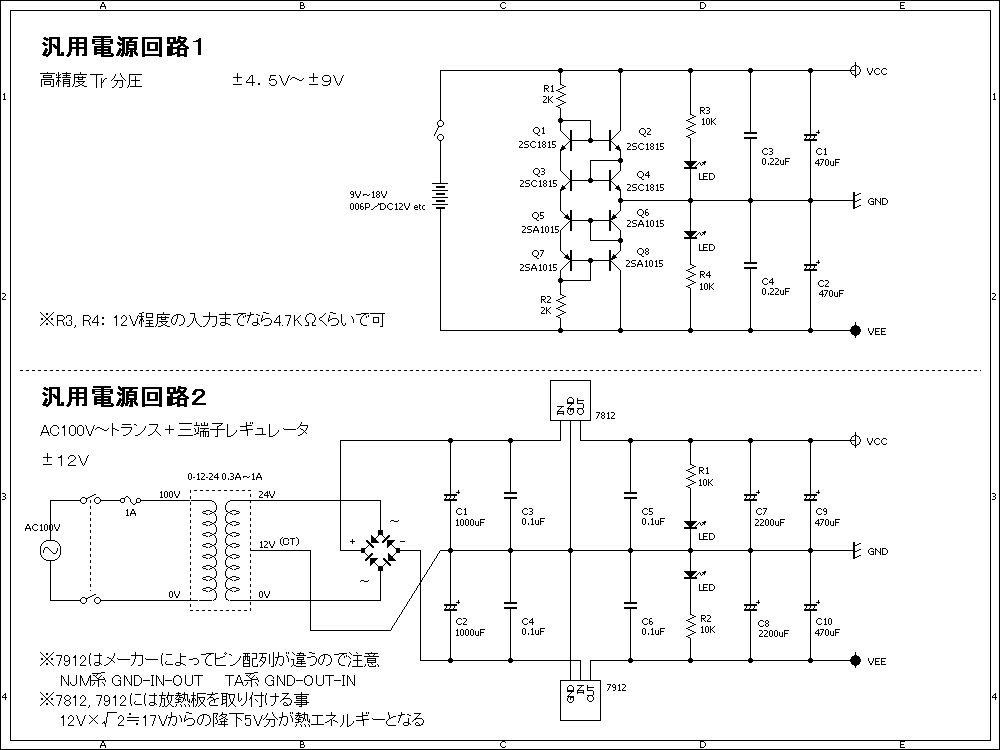 汎用電源回路図 [2007/03/29 更新] 紫稍花さんのページで採用されている高精度ウィルソン分圧方式と 据え置きタイプ用の正負12Vを作るごく一般的なトランス+三端子レギュレータ です。敢えて掲載することは無いんですが、回路図全般に電源部を書き入れる 習慣がないのでひとまとめにしておきます。三端子レギュレータやトランジスタ 全般について言えることですが希にメーカーによってピン配列が異なる事もあり ますので必ずデータシートに目を通してから作成するようにしましょう。これに 気付かずに電源部だけ作るのに1時間近く四苦八苦した経験があります。
回路図中のLEDは動作確認用のインジゲーターにすぎないため省略可能ですが
作成時には入れておいて全て動作確認出来てから外すと電源短絡や配線ミス時に
すぐ気付けます。ジャンパピンなどを入れて運用時はLEDなしにしても良いでしょう。 OPA637を使う場合など、±4.5V〜±6V程度の低電圧では上記の多くの回路で パスコン・位相補償・入力抵抗・出力抵抗・入力バイアスなどを工夫しても発振して しまいうまく動作させるにはもっとノウハウが必要になってきますが、±12Vを使用した 場合は安定動作になってくれる傾向です。OPA627/637系はそもそも電源を大食らいします のでポータブル用途での使用を諦めて据え置きに割り切ったほうが良いのかもしれません。 この回路図では分圧方式は1回路2接点(2P〜3P)の主電源SW、トランス型では AC電源を片方だけ繋いだままにするのは危険なので2回路2接点(6P)のSWを使って いますが、ポップノイズ対策としてリレーを用いる場合、電源ON時はリセットICやコンパレーター に付随させるコンデンサ容量によって数秒遅延させるとして、切るときに1回路多いスイッチを使って 「スイッチで一気に切ってしまえ」というのが案外有用です。次項目にその回路も紹介。 (ダイオードを介して放電速度を調整している回路は確かに素晴らしいのですが電圧降下しますから) トランスを使用するタイプでは三端子レギュレータを使用していますが最低でも15mm×15mm×25mm 程度の放熱板を取り付けて下さい。熱の伝わりをよくするためのシールやゲルシートを挟んだり、 シリコングリスを併用すると良いでしょう。筆者が使ったことのあるトランスは「ノグチトランス PM 2405」「トヨデン HT-2403」「トヨデン HT-241」です。型番が仕様をそのまま示しており、24V仕様の 0.5A, 0.3A, 1A です。ともに12Vタップがあるものです。いわゆる「0V-12V-24V」というやつですね。 センタータップ0Vとした「-12V-0V-12V」という表記のものでも勿論構いません。小型小電力用の汎用で グレードも低いものですがコストパフォーマンスが良く、音質も特に問題になるとは思えません。 音響用のグレード(値段が5倍以上)のものやRコアトランスなどをチョイスする前にまずはこういった 汎用品で作ってみて良いのではないでしょうか。 追記:リレーによるミュート回路を併用する場合には、それだけで5V-100mA近くを消費するため トランスの選択は最低でも0.3Aとしないと定格を越えてしまいますので注意。 |
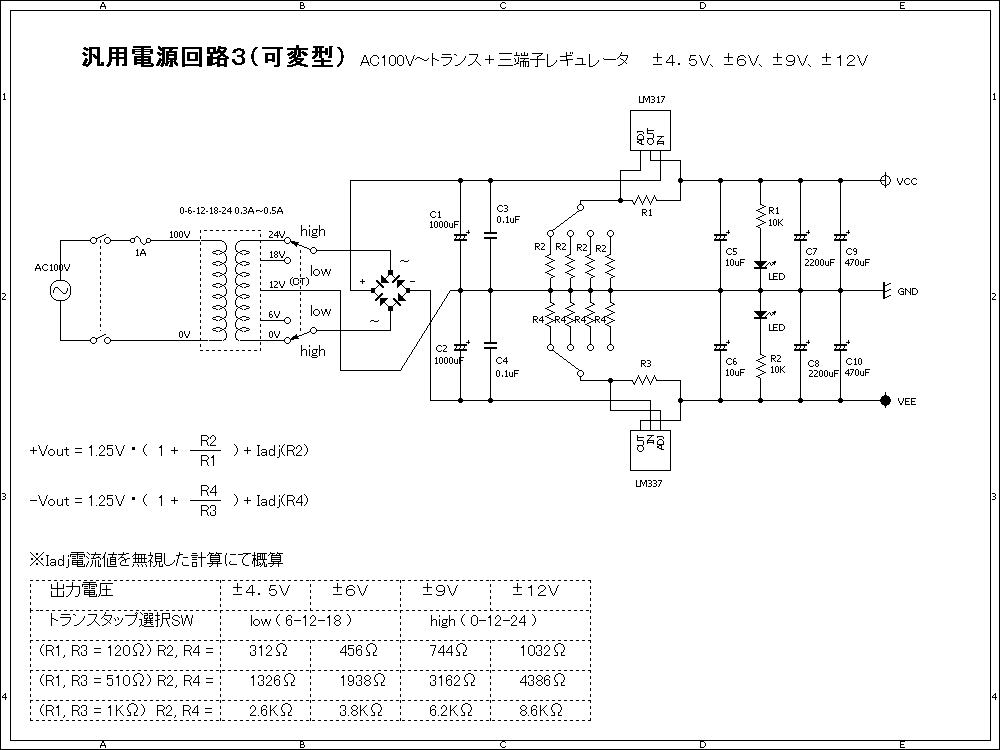 汎用可変電源回路図 

[2007/04/21 更新] 色々とOPAMPを変えてみたり帰還抵抗を変えてゲインをいじっていると供給電圧によってかなり ノイズの出方や音色の傾向が違っている事に気づきます。006P(9V)を想定して±4.5V、カーバッテリー や123A等の12Vを想定して±6V、006P×2(18V)を想定して±9V、一般的なOPAMP全般で使える大きめの 電圧として±12Vを供給できるよう切替式の可変電源を作ってみます。※最大定格電圧が±12Vより低い ものは私はまだ見たことがありません。 LM317/337可変レギュレータはADJ端子とOUT端子間に1.25Vの基準電圧を内部で作り出し、GND間の電圧を 浮動式で可変が出来るものです。Iadj電流値を加算して計算しますが数uA程度ということで誤差範囲として 良いことになっています。基準電圧がかかる部分に120Ω、510Ω、1KΩを選択した場合の各電圧出力用の抵抗値 を書いてみましたが端数が出てきてしまい固定抵抗できちんと揃えるのは難しいかと思います。ですので、 半固定抵抗にして各電圧を調整するのが現実的かと思います。※計算式の分母:データシートでは LM317はR1=240Ω、LM337はR3(R1)=120Ωが一般的な回路定数として記載されていますが、1KΩにしてやっても 問題なく動作します。調整用の半固定抵抗を多回転精密にしてやって入手しやすい抵抗値で選択してやって良い でしょう。
使用するトランスに6Vタップが無い場合は5Vや3Vでも構いません。18Vタップも同様で20Vでも構いません。
降下させる電位差分がLM317/337の熱損失になるので出来るだけ降下電位差を少なくしたいために切替式としています。
降下させる電位差は少なくとも3V程度というのが定石ですが low 側タップで±6Vを出力させる場合、トランスの
出力タップ6Vと18Vでセンタータップ(12V)との電位差が6V×√2で2.5Vくらいの差になっていて少々ギリギリ
です(動いちゃうと思いますが)。 機能上必要ではありませんが、4接点ロータリースイッチといえば3回路のものまで購入しやすい 価格帯で普通に流通していますので、2回路ぶんで電圧指定抵抗の切替を、余った1回路分でLEDでも点灯させて 現在設定されている電圧を明示的にしておくと良いかもしれません。 前項のトランス使用タイプの電源装置も同様ですが、放熱板の選択には一応気をつけて下さい。厳密に計算して吸熱・排熱 の容量をきちんと見積もって見合ったサイズの放熱板を取り付けるのが理想ですが、OPAMP主体の回路に使用する範囲では ケースに入る範囲で出来るだけ大きいものを使用するくらいでとりあえずは大丈夫と思います。もし触っていられなくなるほど 熱くなる場合は放熱板のサイズが不足していますので大きいものに交換、またはノイズ源になるのであまり組み込みたくありません が冷却ファンを併用しましょう。 ※実際に製作したものはロータリースイッチを使わずにジャンパピンで選択するようにして、±6V、±9V、±12Vの切替にして しまいました。高精度ウィルソン分圧のほうを±4.5Vと±6V切替にしてあるので、そっちで済むため省略しちゃいました。
追記:リレーによるミュート回路を併用する場合には、それだけで5V-100mA近くを消費するため
トランスの選択は最低でも0.3Aとしないと定格を越えてしまいますので注意。 ※写真追加:±12V, ±9V, ±6V の選択をジャンパで行う方式にしています。トランスは余裕をもって1A仕様の241。 |
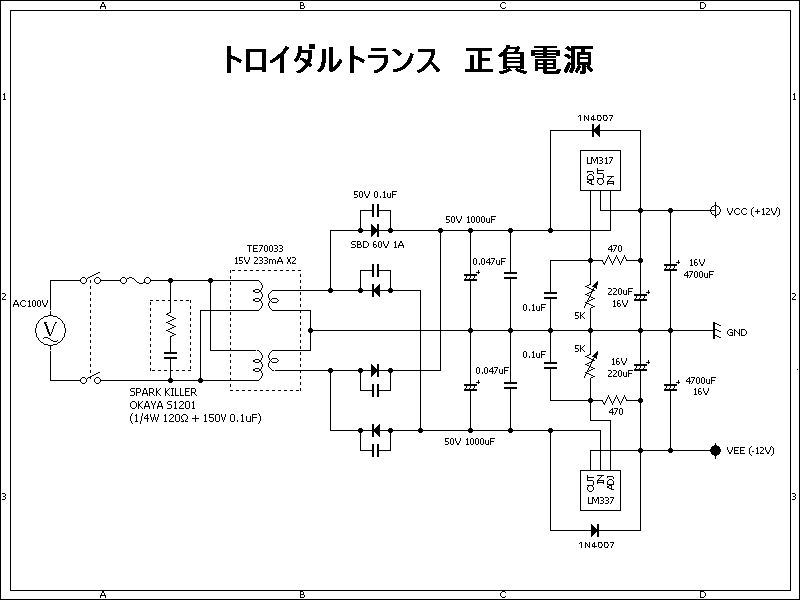 汎用可変電源改回路図 [2009/04/16 更新]
上の可変タイプをあれこれ対策したバージョン。トロイダルトランスを使用し、整流もSBD(ショットキバリアダイオード)を使って両端にフィルムコンを挟んでスイッチノイズを軽減。LM317/337のADJからGNDへのパスコンも挿入。AC100V側はスパークキラーを入れてSW-ON/OFF時のポップノイズとコンセント経由で他の機器から入り込むノイズを軽減。
|
 電源連動ミュート回路図 [2007/03/27 更新] OPAMPの種類によっては電源ON/OFF時にポップノイズを発生し、耳やヘッドホンに悪影響を与えそうなくらい 大きな音がしてしまうものがあります。これは規定電圧より低い電圧での誤動作と言われていますが出なくする ために電源ON時、少し遅延してからヘッドホン出力に導通開始させる回路を利用します。SAITAMAさんのところの 回路を流用し出力にコンデンサを挟んで長めの遅延としています。きちんとした計算方法その他の解説は原典の サイト様を参照下さい。 ON時間の遅延を長めにすることやLED/ダイオードの種類・直列個数の調整が不十分な場合、ON遅延はうまく 動作してもOFF時にポップノイズ発生してしまう場合があります。これを抑止する画期的(?)な方法として、主電源 のスイッチに1回路多いものを用いて切るときにリレーへの電圧供給を遮断して即時OFFするという結構乱暴な 方法を取り入れました。きちんとした計算やオシロによる測定が出来ない素人なりの工夫ですので大目に見てやって 下さい。 |
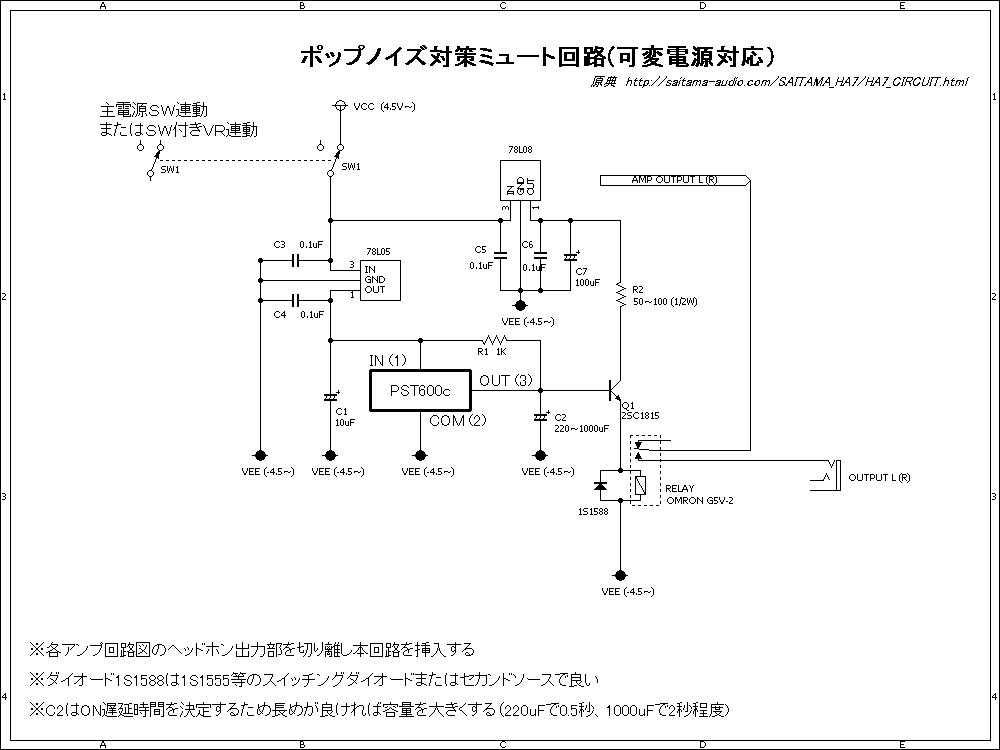 電源連動ミュート回路図(可変電源対応) [2007/04/10 更新] LM317TとLM337Tを使った可変電源に対応させ、リレーの駆動電圧を決定する部分を100mAの5V三端子レギュレータ 78L05にしたものです。また、5V仕様のリレーに最大24V近くを印加してしまうのはさすがに良くないのでコイルへの 電流供給源として78L08を使いました。78L09や78L12でも良いでしょう。上記のミュート回路と違うのはそこだけです。 omron G5V-2(5V)はコイル電流の定格が100mAとギリギリですが、起電力で100mA近くになるものの動作が開始したあとは 実測で80mA程度でしたのでまぁ大丈夫でしょう。余裕をみて78N05など容量の大きいものに変えておいても良いでしょう。 |